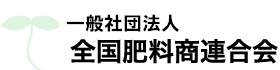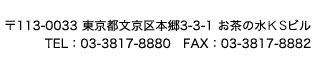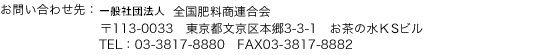一般社団法人
全国肥料商連合会
会長 山森 章二
初めに、各地の自然災害等により被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
日頃、会員の皆様と共に活動させて頂き、また関係者の皆様にはご支援、ご指導を賜り、改めて深謝申し上げます。
私どもは、去る7月3日(木)、4日(金)、北海道札幌市のホテルライフォートにおいて、『期待される北海道〜開拓と変革による成長への道〜』を総合テーマに、石川県金沢市での前回から2年振りとなる第58回全国研修会を開催致しました。農林水産省北海道農政事務所長 小島吉量様らの御来賓より御祝辞を賜り、帯広畜産大学の谷昌幸教授、株式会社大丸松坂屋百貨店専任部長の本田大助様、セイコーマートで有名な株式会社セコマ取締役会長の丸谷智保様よりご講演を賜りました。お蔭様で約140名の多くの方々にご参加頂き、盛会裏に全ての行事を取り行うことが出来まして、感謝の念に堪えません。この紙面をお借りして、ご来賓・講師の皆様、ご参加頂いた方々、また多大なご支援をお願いした北海道地区部会の勝間会長、生沼前会長始め会員の皆様に改めて厚く御礼を申し上げます。
話は変わりますが、例によって以下は私の独り言です。最近決まった今年11月からの全農肥料価格が、値上げではあるものの、現在の原料・為替相場から計算して得られる価格よりある程度安い価格となっており、中でも現在喫緊の課題となっている米用の肥料価格を意図的に抑えたのではないか、と言われています。年2回の全農価格決定に際しては、全農が農水省に事前に報告乃至事実上のお伺いを立てる習慣になっている、とか、全農が農水省から言われる前に忖度することもある、とか言われていますが、今回がどのケースであったかは不明です。
肥料流通の立場からすると、肥料のような農業資材は安く供給できる方が農業生産者様の為になって良いという考え方が基本ですが、あくまでも原料輸入商社・メーカーの健全な事業継続が前提であり、輸入商社・メーカーの採算が悪い状況が続き、商品の供給が細り、売るものが足りなくなるという事態になることは、流通業者としても困るのです。商品の製造・供給が覚束なくなり農水省が打ち出した「食料供給困難事態対策法」(有事の際に国が食料・肥料等の増産経計画を指示)も絵に描いた餅となれば国も困るのです。肥料産業はある時から徐々に弱体化してきた処にここ数年の肥料高騰で原料輸入を担当する商社や製造を担うメーカーが相当疲弊してきており、中には廃業が現実的になったり選択肢に入ってくるような所も出てきている状況で、そこに現実から離れた負担を追加で強いられると、肥料産業の一定規模での縮小が危ぶまれる事態が現実となりましょう。今回の価格設定は、農水省が全農に意図的に要請したのか、米で微妙な立場に立っている全農が忖度したのか、その両方かは不明ですが、これでまた肥料産業の衰退が一歩進むと危惧せざるを得ません。
もう一つ注意すべきことは、数年前から「みどりの食料戦略」を掲げ、2030年までに化学肥料の使用量20%減(2050年までに30%減)を推進している農水省が、ここに来てこれを修正する(或いは説明を変える)準備を始めたかに見えることです。要因は二つです。一つは、化学肥料の使用量(出荷量)が予想以上のスピードで減り、昨年までに2030年の目標を既に達成してしまった(或いはそれにほぼ近い状況になった)ことです。つまり、このまま「化学肥料減」の推進を続けると減りすぎて不都合な状況になる(実はもうそうなっている?)との懸念が急速に高まってきたことです。もう一つは、「化学肥料の20%減/30%減」が米不足の原因の一つになったとの指摘が出始めたことです。農水省全体の方針である「みどりの戦略」に則って肥料関係部局が肝入りで行った政策が実は米不足の原因であったなどということは、仮にそれが事実だとしても、農水省としてはそれを容易に受け容れる訳には行きません。「化学肥料の低減」「畜ふん堆肥・下水汚泥肥料の推進」はなぜ行われ、現在どういう状況になっており、これからはどうするのか、近く農水省が新たな説明を始めるのではないか、と推測しています。こう見てくると、化学肥料の減り過ぎは問題であるということがはっきりとしてくるので、前段の化成肥料価格の上げ幅の抑制は、化学肥料の使用量(出荷量)を少し回復させたい、との農水省(・全農)の希望が反映されていると考えると合点が行くのかも知れません。農水省の舵取りが難しいことは理解できますが、「農水省は生産者と全農・農協のことしか考えていない」と言われないように、食料安全保障の一角を担う原料輸入商社・メーカー・流通業者の経営状態への配慮・目配りもお願いしたいと思います。
最後に、尋常ではない猛暑が続く中、皆様には呉々もご自愛くださいますようお願い致しまして、暑中お見舞いのご挨拶とさせて頂きます。引続き当会に対するご指導、ご支援の程何卒宜しくお願い申し上げます。
あけましておめでとうございます。旧年中は弊会の活動に多大なるご理解とお力添えを頂きまして、誠に有難うございました。本年も引続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
初めに、各地の自然災害等により被災された方々には謹んでお見舞い申し上げます。
次に、昨年も弊連合会が主催する施肥技術マイスター・シニアマイスターになって頂く為の「施肥技術講習会」の開催等に当たり、多くの方々のお世話になりました。改めて厚く御礼申し上げます。ご好評を頂いております施肥技術講習会は、今年は2月25/26日(水/木)(静岡)、5月中/下旬(東京)、11月(福島郡山(予定))の計3回行います。また、今年は当会創立70周年にあたりますので、9月17日(木)に東京の都市センターホテル(平河町。地下鉄永田町又は麹町駅至近)にて、創立70周年記念式典を開催(全国研修会と同時開催)させて頂きます。昨年7月3/4日(木/金)は北海道・札幌での全国研修会に多数の方々にご参加頂きまして誠に有難うございました。今年の9月も奮ってご参加ください。
さて、以下は執筆の時点(令和7年12月12日)での私の独り言です。
(1)米増産への方向転換取り消し
高市政権になって農水大臣が代わられ、石破政権の最後に打ち出された米増産への方向転換は瞬時に取り消されました。鈴木大臣の地盤は山形という農協が強い県で、現在の全農の経営管理委員会の会長はJA山形中央会の会長ですから、米の増産に消極的な態度をとらないと次の選挙でどうなるかわからない、という立場なのかと推測されますので、そう驚くことではありません。奇妙なのは、高市総理がこの件に積極的には触れないだけでなく、マスコミも突っ込まない、という“完璧な対応”です。石破政権下の選挙では緩んだとも言われる全中・全農からの支援を回復し次の選挙に臨む、という政権党の本気度が伺えるということでしょうか? 残念ながら、緊急事態も想定した米の増産への方向転換が遠のいたことだけは確かなようで、現在の全中全農体制温存・真の農政改革先送りがもう暫く続くようです。
(2)「農業支援サービス事業」の開始
高齢化等で農業生産者さんが他の人に依頼したい農作業を請け負うことを業として行う者に、必要な機械の購入代金の半額を国が補助するという新制度が令和7年1月から開始されました。農水省の予算申請額に対し財務省が減額して承認するというのが通常のパターンですが、本件は農水省の申請額より遥かに多額の100億円が財務省から承認されたようで、この政策に対する財務省の期待が大きいことが伺えます(新年は約150億円?)。これに呼応して、農水省も10月に外郭団体の「(一社)農林水産航空協会」(ヘリ・ドローン推進)を「(一社)農林水産航空・農業支援サービス協会」に発展的に改組し、今後の推進体制を整えました。今後農業支援サービス事業の拡大は一つの流れになると思われ、当会の会員の肥料商さんにもこの支援金を活用してサービスを開始するところが出てきています。新年早々に募集が再開される見込み(未定)ですので、再開された際には、本支援事業の活用をご検討されては如何がでしょうか。
(3)「被覆肥料(尿素)の殻の問題」
農水省は予て、環境上の理由から、「2030年までに殻の材質を生分解性プラスチックに変えたい」との意向をもっており、メーカー等もその方向で尽力中ですが、生分解性プラスチックで従来品同様のシグモイド型の溶出曲線を完全に達成できる被覆肥料を2030年までに開発できるかどうか微妙な状況で、達成できなかった場合にどうなるのかが関心事となっています。農水省は、益々進行する猛暑化の中でプラスチックの被覆肥料を使えなくなる事態は現実的ではない、との大方の見方に大筋同調しているようで、完全な生分解性プラスチックでないと絶対に認めないとの方針は打ち出しにくいと考えているようです。加えて、プラスチックの環境問題に係る世界会議(INC)もなかなか纏まりそうもない現状も踏まえ現時点で新たな方針を打ち出すのは時期尚早との考えもあり、当分様子見ということではないかと思われます。引続き注視します。
終わりに、今年一年が皆様とご家族様にとって新たなご隆盛の始まりとなりますことを祈念して新年のご挨拶とさせて頂きます。
一般社団法人 全国肥料商連合会
会長 山森 章二