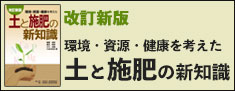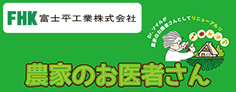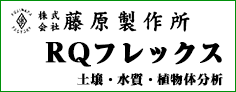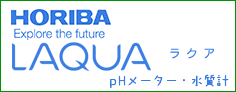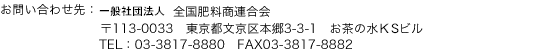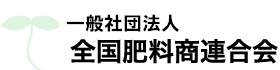
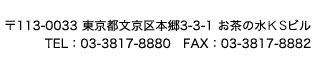
- 【国内肥料資源の活用に関する相談窓口】
(一社)全国肥料商連合会では、国内資源由来肥料の利用拡大に関する関係者からの相談、
製品開発、流通促進、普及に対する事業推進のための相談窓口を令和5年6月1日から設置します。
お問合せ先は、下記の通りです。
記
連絡先: TEL 03−3817−8880
担当者: 西出 邦雄
E-mail: nishide★zenpi.jp
※ ★ は @ に置き換えて下さい
- 緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の
流出防止に向けた取組方針
一般社団法人 全国肥料商連合会(以下、「当会」)は、農林水産省農産局長より令和4年1月24日付「緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の流出防止に向けた対応の強化について」と題する要請書を受領致しました。
内容は、下記二点の依頼です。
1.被覆殻の流亡防止対策の徹底
2.新たな代替施肥技術の導入・実証等の取組への参画
当会は、2019(平成31)年3月8日付で「使用済みプラスチックの排出量抑制を維持強化する取組」(「プラスチック資源循環アクション宣言」を参照)を発出したとおり、肥料の役目を終えた被膜の一部が圃場から流出し海洋漂着プラスチック(所謂マイクロプラスチック)として環境への負荷を加える可能性があるとの指摘、また、海洋漂着プラスチック問題への国際的な取り組み強化の要請に応えるため、これまでも肥料流通団体として次の活動に取り組んでまいりました。
(1)被覆肥料の殻が農耕地から流出することを極力防止するため、肥料製造業者が推進する包材などの記載への注意喚起等により、会員の意識を高め、農業生産者への協力要請を強化し、環境保護活動の普及啓発に努める。
(2)被覆肥料の殻の環境中での分解性向上を肥料製造業者に要求すると共に、被覆樹脂使用量の削減に向けた技術開発に努める肥料製造業者と協力し、環境にやさしい被覆肥料の普及に努める。
(3)被覆肥料以外の省力タイプの肥料など、他の機能性肥料の活用場面の普及拡大に努める。
今般上記1.のように農林水産省より改めて「被覆殻の流亡防止対策の徹底」の要請がございましたので、被膜殻の流亡防止対策の徹底に付きましては、当会の会員に対し再度周知した処です。
また、上記2.の「新たな代替施肥技術の導入・実証等の取組への参画」に付きましては、現在持続農業法のもと農林水産省が推奨する被覆肥料使用に付いての今後の見直しや、被覆肥料メーカーによる代替技術の開発等の今後の進展状況も踏まえて、当会も取組に積極的に参画して行く所存です。
今後とも、当会の活動にご理解を賜り、引続きご指導、ご支援を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
令和4年2月25日一般社団法人 全国肥料商連合会
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目3番1号
お茶の水KSビル 3階
電話:03-3817-8880 / FAX:03-3817-8882
Topics
 ◆【訃報(有)野矢商店 野矢善章会長 ご逝去】
◆【訃報(有)野矢商店 野矢善章会長 ご逝去】
滋賀県野矢商店の野矢善章会長が、6月24日に82歳でご逝去されました。
野矢善章会長は、長年にわたり全肥商連の理事として当会の事業運営に多大なるご協力を賜りました。また滋賀県部会長として、滋賀県のみならず近畿地方の肥料業界を長きにわたり牽引して頂きました。謹んでお悔やみ申し上げます。
 ◆【令和4年度全肥商連第7回理事会】開催日時・場所のお知らせ
◆【令和4年度全肥商連第7回理事会】開催日時・場所のお知らせ
議案はまだ検討中ですが、開催日時・及び場所は次の通りにて行う予定ですので、理事・監事の皆様には万障お繰り合わせの上ご出席をお願いします。
日 時:令和5年8月26日(月)12:30〜15:30
場 所:めっきセンター4階会議室
※東京都鍍金(めっき)工業組合内にある貸会議室です
東京都文京区湯島1-11-10
東京都鍍金工業組合 アクセスマップはこちら ⇒ https://www.tmk.or.jp/2_gaiyou/access.html
 ◆【第40回施肥技術講習会(第13回基礎・実学混合コース)】開催のお知らせ
◆【第40回施肥技術講習会(第13回基礎・実学混合コース)】開催のお知らせ
第40回施肥技術講習会(第13回基礎・実学混合コース)を以下にて開催予定しております。
日 時:令和6年11月7日(木)〜8日(金)
場 所:燕三条地場産業センター マルチメディアホール
新潟県三条市須頃1-7
募集人数:100名
詳細は、8月中〜下旬に募集要項にてお知らせする予定です。
 ◆【国内肥料資源の利用拡大に向けたマッチングフォーラム】今後の開催のお知らせ
◆【国内肥料資源の利用拡大に向けたマッチングフォーラム】今後の開催のお知らせ
「国内肥料資源の利用拡大に向けたマッチングフォーラム」に付きましては、昨年6月(東京)、9月(熊本)、本年1月(宮城)、3月(愛知)で開催されましたが、今後のスケジュールに付きましては、下記の予定です。
1)シンポジウム in 近畿 8/28(水)@大阪府 エル大阪
2)マッチングフォーラム in 中国四国 9/25(水)@広島県 広島産業会館
3)マッチングフォーラム in 北海道 12/4(水)@北海道 アクセスサッポロ
<あわせてご案内いたします>
当イベント開催事務局では、国内肥料資源の利用拡大に関する関係事業者からの相談窓口を設置しており、全肥商連からも東京農大後藤逸男名誉教授と共に出展しております。詳細はWebサイトをご確認ください。
https://www.kokunai-hiryo.com/
なお、相談窓口は無料でご利用いただけますが、「国内肥料資源の利用拡大に向けた全国推進協議会」の会員登録が必要でございますので、会員登録されていない方は、以下の農林水産省HPから会員登録をお願いいたします。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/kokunaishigen/zennkokusuishin.html
【問い合わせ先】
株式会社リベルタス・コンサルティング
〒102-0085 東京都千代田区六番町 2-14 東越六番町ビル
Tel:03-6262-1493(平日10:00〜17:00)
Fax:03-6262-3040
E-mail: kokunai-hiryo@libertas.co.jp
 ◆【第39回施肥技術講習会@東京】開催のご報告
◆【第39回施肥技術講習会@東京】開催のご報告
掲題の講習会につき、予定通り5月29日〜30日に東京農大世田谷キャンパスにて開催致しました。今回は特に遠方の為会場受講できない方を対象としたWeb受講も同時に行い、最終的に108名の方にご参加頂きました、誠にありがとうございました。
また今回講師を交えた意見交換会を4年振りに開催し34名の方にご参加頂き大変有意義な機会を持つことが出来ました、ご参加頂いた方々には深謝申し上げます。
第39回講習会の様子はこちら⇒ https://www.zenpi.jp/katudou/39th_meister.html
次回の第40回施肥技術講習会は、本年11月7日〜8日に新潟県三条市にて開催予定で応募要領につきましては、8月下旬にご案内予定です。
また第41回は来年(2025年)2月下旬に岡山にて開催すべく準備を進めております。
 ◆【臨時社員総会】理事・監事の辞任及び就任に関する書面決議開催と結果報告
◆【臨時社員総会】理事・監事の辞任及び就任に関する書面決議開催と結果報告
4月1日付で、臨時の社員総会を書面にて開催致しました。議案は理事1名並びに監事1名の選任です。
理事である三菱商事株式会社 宮澤正己氏並びに監事であるシーアイマテックス(株)土川光男氏は4月1日付けの所属会社の人事異動で弊会の理事及び監事を辞任されることとなり、宮澤氏の後任理事として安田剛氏、土川氏の後任監事として吉田和弘(わこう)氏を選任すべく、社員総会にご承認を求めたものです。
書面社員総会にてご審議頂いた結果、全会一致で安田氏が理事、吉田氏が監事として承認されましたことをご報告申し上げます。
また、この書面総会後に書面理事会を開催し、安田氏は宮澤氏の後任として副会長に選任された事を併せてお報告致します。
 ◆【岡山大学 馬建鋒(ま けんぼう)教授】国際肥料協会(IFA)から受賞
◆【岡山大学 馬建鋒(ま けんぼう)教授】国際肥料協会(IFA)から受賞
昨年5月より、本会施肥技術講習会の講師を務めて頂いております岡山大学資源植物科学研究所教授の馬建鋒先生が、昨年11月カタールのドーハで開催された国際肥料協会(IFA)の年次大会に於いて、2023年度の
「The IFA Norman Borlaug Plant Nutrition Award」を受賞されましたので、遅ればせながらご報告申し上げます。
国際肥料協会(IFA:International Fertilizer Association )は1927年に設立された、79か国以上に400人以上の会員を有する国際機関です。この賞は「緑の革命」の父・ノーベル賞受賞者のノーマン・ボーローグ氏の名に因んだ賞で、植物栄養学の発展に多大な貢献をした一人に毎年授与されるものです。
馬先生は長年植物のミネラル輸送機構に関する研究を行い、数々のミネラル輸送体を世界に先駆けて解明していることが国際的に高く評価され、今回の受賞となりました。
馬先生には本会の施肥技術講習会に於いて、植物のミネラル栄養やミネラル輸送体についてご講義頂いており、今回の受賞に付きまして心よりお祝い申し上げます。
岡山大学のホームページ:
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12685.html
 ◆【国内肥料資源の利用拡大に向けた全国協議会】第2回幹事会のご報告
◆【国内肥料資源の利用拡大に向けた全国協議会】第2回幹事会のご報告
3月15日農林水産省にて「国内肥料資源の利用拡大に向けた全国協議会」の第2回幹事会が開催され、幹事団体である弊会も出席致しました。本会議は非公開で開催されましたが概要は以下の通り。
<出席関係者(団体)>
全国推進協議会 幹事 : (一社)全国農業協同組合連合中央会
全国農業協同組合連合会
(一社)日本有機資源協会
(一財)畜産環境整備機構
(公社)日本下水道協会
(一社)全国肥料商連合会
農林水産省 : 農産局技術普及課 課長
農産局技術普及課 肥料調整官
農産局農業環境対策課 課長
畜産局畜産振興課 課長
国土講習省 : 下水道部下水道企画課 室長
<議事及び概要>
1.全国推進協議会の目的等の確認:
国内肥料資源の利用拡大を推進すべく国内肥料原料供給者・肥料製造事業者・肥料利用者・関係団体・研究機関・地方公共団体等幅広い業界に協議会に参加するよう働きかけことを目的とする。令和6年3月8日時点で389の会員登録に到った。
2.全国推進協議会における令和5年度の取組実績の報告:
(1)広域的な連携の取組のサポートをすべく、国内肥料資源の利用拡大に向けたマッチングフォーラムを以下の通り4回開催した(数字はおおよその値)。
| 開催地 | 参加者+来場者 | 基調講演+発表事例席数 |
|---|---|---|
| ・In東京(東京都大田区) | 600名 | 80+50 |
| ・In九州(熊本県益城郡) | 600名 | 192+72 |
| ・In東北(宮城県仙台市) | 400名 | 250 |
| ・In東海(愛知県名古屋市) | 350名 | 250 |
(2)生産現場での利用拡大の向けた取り組みを推進すべく
(1)国内資源由来肥料に関する取組内容等の発信を行った。
→農林水産省の全国推進協議会サイトに取り組み事例を掲載
(2)国内肥料資源推進ロゴマークを作成した。
→全国推進協議会会員企業が利用可とした。
(3)先進事例の横展開・関連情報を提供すべく
(1)全国推進協議会HPにおいて、関係者による情報や知見をタイムリーに発信
(2)国内資源由来肥料の活用事例をHPで公表(現在97事例)
3.令和6年度の取組方針(案)の表明:
基本的に上記令和5年度の(1)(2)(3)を継続する方針。これに加え、「国内肥料資源活用アワード(賞)を創設する予定。関係事業者間のマッチングフォーラムについては、北海道・中四国地域等での開催を予定。また国内肥料資源の需給を調査しMAPを作成する事を考えたい由。
 ◆【第38回施肥技術講習会@名古屋】開催のご報告
◆【第38回施肥技術講習会@名古屋】開催のご報告
掲題の講習会を予定通り令和6年2月20日(火)〜21日(水)にウインクあいち(愛知県産業労働センター)にて開催致しました。募集100名のところ最終的に81名の方に受講頂きました。この場をお借りして受講頂いた皆様には御礼申し上げます。
講習会の様子はこちら⇒ https://www.zenpi.jp/katudou/38th_meister.html
次回第39回の施肥技術講習会は、5月29日〜30日に東京農業大学世田谷キャンパスにて開催すべく準備を進めております。応募要領につきましては、3月下旬頃にご案内させて頂く予定です。
また第40回施肥技術講習会は、本年11月7日〜8日に新潟県三条市にて開催予定しております。第40回の応募要領につきましては、8月下旬にご案内予定です。
 ◆【国内肥料資源活用拡大に向けた「取組事例集」発行
◆【国内肥料資源活用拡大に向けた「取組事例集」発行
世界的な肥料需要の高まり、原油・天然ガスの価格高騰他諸情勢の影響により、海外肥料原料の供給不安が懸念されています。
国では昨年度より「国内肥料資源利用拡大対策事業」を立ち上げ、実現に向けた取組を実施しておりますが、その一環として弊会もホームページの掲載や東京都、熊本市、仙台市で開催されたマッチングフォーラムに於いて、国内肥料資源の活用に関する相談窓口を設置し協力させて頂いております。
この度、本事業についてマッチングフォーラムに出展された本会会員メーカーを主として紹介させて頂く「取組事例集」を発行しましたのでご案内致します。
本書が関係者の皆様方のご理解を深め、お役に立てることが出来ることを願っております。
【詳しくはこちらをご参照下さい】
国内肥料資源活用拡大に向けた取組事例集
(A4判、36頁、オールカラー)
PDFを以下からダウンロードできます。
https://www.zenpi.jp/gyokai/pdf/hiryosigenjirei202402.pdf
 ◆【令和5年度第2回理事会】開催のご報告
◆【令和5年度第2回理事会】開催のご報告
令和5年度第2回理事会を予定通り去る1月17日に東京ガーデンパレスにて開催、以下2議案が上程され審議されました。
第1号議案:「令和5年度特別プログラム」承認の件
第2号議案;準会員入会承認の件
第1号議案については、9件の案件申請があり、一部金額修正の上承認されました。承認金額については、当該申請部会に個別に連絡済みです。
第2号議案については、昨年9月に解散した奈良県部会より2社((有)藤万、安川肥料店)が準会員としての入会申し込みがあり、審議の結果入会が承認されました。
報告事項として、
(1)令和5年度8-12月収支中間報告
(2)基本問題検討委員会の検討状況
(3)施肥技術講習会の開催状況・予定
(4)肥料・農政の最新動向
について、議長より報告がありました。
 ◆【全肥商連・全複工 合同講演会】開催のご報告
◆【全肥商連・全複工 合同講演会】開催のご報告
理事会後に、コロナ禍にて中断を余儀なくされておりました恒例の全複工との合同講演会を4年振りに開催、約180名の関係者にご参集頂きました。
講演概要は以下の通りです。
<講演>
演題:食料・農業・農村基本法の改正の方向性と肥料施策
講師:農林水産省農産局技術普及課長 吉田 剛氏
<特別講演>
演題:日本政治の課題
講師:自由民主党農林部会長 細田 健一衆議院議員
吉田氏には、最近の農政の動向と現在策定中である今後の施策の基本方針、細田衆議院議員には日本の政治の問題点・課題について同議員の視点でオフレコのエピソードを交えながらご講演頂きました。
講演会の模様はこちら ⇒ https://www.zenpi.jp/katudou/gasikoukan2024.html
 ◆【全肥商連・全複工 合同新年賀詞交歓会】開催のご報告
◆【全肥商連・全複工 合同新年賀詞交歓会】開催のご報告
講演会の後、掲題の合同賀詞交歓会を東京ガーデンパレス「高千穂の間」にて開催致しました。こちらも4年振りの開催となり全複工・全肥商連会員、行政、業界団体、各方面からの来賓など約170名の方にご来場頂きました。
全肥商連山森会長の能登地震被災者への哀悼の意の表明と主催者挨拶に始まり、以下ご来賓のご祝辞を頂きました。
・石破茂衆議院議員(元防衛・農水・地方創生大臣)
・武部新衆議院議員(衆議院法務委員長、元農水副大臣)
・細田健一衆議院議員(自民党農林部会長、元経産・内閣府副大臣)
・宮路拓馬衆議院議員(自民党国会対策副委員長、元内閣府政務官)
・安岡澄人 農林水産省消費安全局長
・土屋博史 経済産業省製造産業局素材産業課長
ご来賓挨拶後、全複工溝口会長の乾杯のご発声で開宴、会場は4年振りということもあり終始熱気に包まれ盛会のうちに終えることが出来ました。
賀詞交歓会の模様はこちら ⇒ https://www.zenpi.jp/katudou/gasikoukan2024.html
 ◆【令和6年新年のご挨拶】
◆【令和6年新年のご挨拶】
令和6年新年の会長挨拶を掲載しました。
会長挨拶はこちら ⇒ https://www.zenpi.jp/sosiki/index.html
 ◆【賛助会員の動画配信のご紹介】
◆【賛助会員の動画配信のご紹介】
弊会賛助会員であるエムシーファーティコム社より、同社がYouTubeで配信している動画を弊会関係者に紹介して欲しいとの依頼があり、以下ご紹介いたしますので、ご興味のある方は是非ご視聴願います。また同様に動画の紹介をご希望される方は本部にご連絡頂ければメールマガジンにてご紹介させて頂きます。
★MCFC_動画チャンネル - YouTube
https://www.youtube.com/@mcfc_3121
★プランター栽培やってみませんか - YouTube
https://www.youtube.com/@user-bk7ql5rh9p
 ◆【(一社)全肥商連第13回定時社員総会】開催のご報告
◆【(一社)全肥商連第13回定時社員総会】開催のご報告
第13回定時社員総会につきましては、9月12日13時より東京ガーデンパレスにおいて4年ぶりに対面で開催致しました。総議決数50票の内28票の出席、21票の委任状(棄権1票)となりました。まず報告事項として「令和4年度事業報告」と「基本問題検討委員会設置準備の件」について報告及び説明ありました。次に決議事項として「令和4年度収支決算報告と貸借対照表及び損益計算書承認」「令和5年度事業計画」「令和5年度収支予算案」「令和5年度会費分担及び徴収方法決定」「常勤理事の退職金上限設定」「理事選任」の議案が上程され、全ての議案が賛成多数で原案通り承認可決されました事をご報告申し上げます。
また総会中14時15分に一旦総会を中断し、総会で選任された理事による理事会を開催し、役員の選出を行いました。
「令和5年度事業計画・収支予算」につきましては、従来通りホームページ(組織案内)に掲載致しますのでご参照頂ければと存じます。
主な決議事項は以下の通りです。
□『今後の主な行事予定』
・令和5年10月24(火)〜25日(水)
第37回施肥技術講習会(基礎・実学混合コース)札幌
・令和6年1月17日(水) 令和5年度第2回理事会
−同− 賀詞交歓会 東京ガーデンパレス(予定)
2月21日(火)〜22日(水) 第38回施肥技術講習会
(基礎・実学混合コース)名古屋(予定)
5月/6月 第39回施肥技術講習会(基礎・実学混合コース)東京(予定)
8月中旬 令和5年度第3回理事会(予定)
□『特別プログラム』
コロナ禍の影響で令和1〜4年度に実施できなかった案件は7件で予算未消化額は123万円となりました。この未消化予算については一旦白紙に戻させて頂く事となりました。
令和5年度の特別プログラム予算については、150万円にて総会で決議されました。
□『理事選任』
今総会をもって理事の任期が満了となりますので、理事の選任を行い以下の方が理事に選任されました(敬称略)。
| 氏 名 | 所 属 | 重任/新任 |
|---|---|---|
| 菅原 圭三 | 三井物産(株) | 重任 |
| 宮澤 正己 | 三菱商事(株) | 重任 |
| 得井 理史 | 住商アグリビジネス(株) | 重任 |
| 長谷川 惠章 | 昭光通商アグリ(株) | 重任 |
| 生沼 直敏 | (株)愛農 | 重任 |
| 勝間 真也 | (株)丹波屋 | 重任 |
| 渡辺 嘉章 | (株)渡嘉商店 | 重任 |
| 福田 大輔 | (株)福田商会 | 重任 |
| 小嶋 正八郎 | 小嶋商事(株) | 重任 |
| 山本 真一 | 山本商事(株) | 重任 |
| 高橋 禮司 | 高橋商事(株) | 重任 |
| 柴沼 啓子 | (株)アグリサクセス柴沼 | 重任 |
| 塩野谷 憲司 | (株)塩野谷周太郎商店 | 重任 |
| 宮本 和明 | 宮本商事(株) | 重任 |
| 五十嵐 康之 | (株)ネイグル新潟 | 重任 |
| 水谷 久美子 | 日本オーガニック(株) | 重任 |
| 豊田 富士雄 | 豊田肥料(株) | 重任 |
| 高松 正敏 | 師定(株) | 重任 |
| 加藤 眞八 | (株)カネ八商店 | 重任 |
| 高橋 久夫 | 園田商事(株) | 新任 |
| 柴田 洋志 | 日植アグリ(株) | 重任 |
| 吉見 誠記 | (株)ヨシミ | 重任 |
| 立石 晃一 | 立石商事(株) | 重任 |
| 宮原 茂行 | (資)宮原商店 | 重任 |
| 安武 広信 | ヒノマル(株) | 重任 |
| 山森 章二 | (一社)全国肥料商連合会 | 重任 |
| 西出 邦雄 | (一社)全国肥料商連合会 | 重任 |
| 村口 典行 | (一社)全国肥料商連合会 | 重任 |
尚 本総会終了をもって、小浦市郎様(小浦産業(株)代表取締役社長)は理事を退任されることになりました。小浦様には在任期間中に大変お世話になりました、この場をお借りして御礼申し上げます。また新任として高橋久夫様が就任されました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
【全肥商連令和5年度第1回理事会】開催のご報告
前述の通り第13回定時社員総会中に、令和5年度第1回理事会を開催致しました。第1号議案である役員選任人事を決議し、次の通り承認されました(敬称略)。
| 会長(代表理事) | :山森 章二 | (全肥商連) |
| 副会長 | :菅原 圭三 | (三井物産株式会社) |
| ; | :宮澤 正己 | (三菱商事株式会社) |
| ; | :生沼 直敏 | (株式会社 愛農) |
| ; | :山本 真一 | (山本商事株式会社) |
| ; | :豊田 富士雄 | (豊田肥料株式会社) |
| ; | :加藤 眞八 | (株式会社 カネ八商店) |
| ; | :安武 広信 | (ヒノマル株式会社) |
| 専務理事 | :西出 邦雄 | (全肥商連) |
| 常務理事 | :村口 典行 | (全肥商連) |
第2号議案として、基本問題検討委員会を設置することが全会一致で承認されました。本委員会の委員の構成や進め方については、10月以降にWeb等で打ち合わせていくことになりました。
 ◆【第57回全国研修会開催@金沢市】開催のご報告
◆【第57回全国研修会開催@金沢市】開催のご報告
▼コロナ禍により一時中断し3年越しとなりました「第57回全国研修会」は「持続的地域農業の創生〜加賀・能登から活力を!〜」の総合テーマの下、7月6日(木)〜7日(金)に金沢ニューグランドホテル(石川県金沢市)において予定通り開催致しました。
1日目は講演を中心に行い、2日目は希望者のみを対象とした金沢市の集荷場、市場、史跡のツアーと致しました。
金沢市での本研修会は、元々令和2(2020)年7月に開催を予定しておりましたが、コロナ感染症の流行が長引き、延期を余儀なくされておりました。その間においても、全肥商連石川県部会(会長:日栄商事(株)社長中村哲郎氏)の会員の皆様と実現に向けて打合せを重ね、漸く本年開催することが出来ました。約130名の、石川県部会関係者並びにご参集頂いた皆様にはこの場をお借りして御礼申し上げます。
▼研修会では、開講式で中村全国研修会実行委員長の開会の辞、全肥商連 山森会長の主催者挨拶の後、石川県知事馳浩様並びに農林水産省北陸農政局長川合規史様のご来賓のご挨拶・ご祝辞により開催致しました。
川合農政局長ご出席の模様につきましては、北陸農政局HP「フォトギャラリー」にも掲載されました。
▼総合テーマのキーワードは「土壌」と「持続的農業」です。
「持続的農業」を実現するには「土」「土壌」という基本に今一度立ち返る必要があるのではと考えました。
そこで、研修会では初めに基調講演として、森林総合研究所 主任研究員 藤井一至様の「土の5億年に学ぶ持続的な食料生産とは」という演題でご講演を頂きました。
「土とは何か?」「土と生命 5億年の共進化」「日本の土」といった土そのものの話から、「土と肥料の関係性」「土の肥沃度を維持するために」といった土壌の肥沃度の話、そして「土を生かすには」「土に必勝法なし」「日本の土と食料安全保障」ということで「完璧な土・農法といったものはなく、土を見ながら試行錯誤を楽しむ」という興味深く含蓄のあるご講義を頂きました。
続きまして、石川県農林総合センター所長 藪哲男様より「石川の土と恵み〜持続的農業に向けた土壌研究とオリジナル品種の開発〜」との演題で、物理的・化学的に肥沃とは言えない能登の土壌をどのように改良してきたか、石川県のブランド農産物「百万石の極み(米)」「ルビーロマン(ぶどう)」「加賀しずく(梨)」などの開発のエピソードをご披露頂きました。
最後に、全肥商連石川県部会の理事で石川スズエ販売株式会社 代表取締役社長杭田節夫様による「農家の強力なパートナーとなるために〜農機と肥料の二刀流経営〜」との演題でご講演を頂きました。農機販売をしていたところ農家の要請でカルシウム肥料を販売したところ倒伏が大幅に減り良質の米が出来、その良質の米に付加価値をつけて販売するため、おにぎり店の経営まで事業を拡大しているという興味深い話をご披露頂きました。
▼研修会終了後、懇親会を開催、94名が参加されました。
石川県部会 川上産業株式会社 茨木陽介様の司会進行にて、和太鼓集団OTO soundによる加賀太鼓の演舞でのオープニングの後、石川県部会理事 (株)フクムラ 福村篤郎様による乾杯の音頭で懇親会が開宴。3年越しの大人数の会ということもあり、会場は大変な熱気で包まれ懇親会は大盛会となり、全肥商連副会長で福島県部会長の山本商事(株)山本真一様の関東一本締めにより散会となりました。
▼2日目は、希望者による「金沢市の農業・市場視察コース」「石川県の文化・史跡視察コース」の2種類のバスツアーを開催。快晴に恵まれましたが、37℃の猛暑の中のツアーとなりました、参加者の皆様大変お疲れ様でした。
第57回全国研修会の模様 ⇒ https://www.zenpi.jp/katudou/zenkokuken2023.html
 ◆【国内肥料資源の利用拡大に向けたマッチングフォーラムin東京】開催のご報告
◆【国内肥料資源の利用拡大に向けたマッチングフォーラムin東京】開催のご報告
前号でご連絡した掲題のマッチングフォーラムが、6月26日東京都大田区産業プラザで開催されました。農水省の発表によりますと、ブース出展者を含め500名以上が集まり盛会な会となり、業界関係者の関心の高さを感じた次第です。また、本会員メーカーのブースも十数社出展されており、全肥商連会員や賛助会員の多くの方々も来訪されておりました。本部からも相談窓口として東京農業大学後藤名誉教授にご協力頂き、ブースを設営し対応させて頂きました。
フォーラムの様子はこちら⇒ https://www.zenpi.jp/siryo/pdf/matchingforum.pdf
 【令和5年 全肥商連十大ニュース】
【令和5年 全肥商連十大ニュース】
「令和5年全肥商連十大ニュース」は次の通りです。
(1)肥料高騰対策とその後
(2)肥料輸入原料備蓄
(3)国内未利用資源活用
(4)記録的な猛暑と農産物への影響
(5)全肥商連事業関係
(6)ハマスVSイスラエル武力衝突と長期化するロシアのウクライナ侵攻
(7)新型コロナ5類に移行、インバウンド復活、オーバーツーリズムの懸念
(8)円安・株高
(9)WBC日本優勝、大谷翔平ホームラン王達成・2度目の満票MVP
(10)藤井聡太名人将棋8冠達成
*本文はこちら ⇒ 令和5年全肥商連十大ニュース![]()
 ◆【施肥技術講習会】今後の開催予定
◆【施肥技術講習会】今後の開催予定
今後の施肥技術講習会は、以下の開催を検討しております。
・第40回施肥技術講習会(第13回基礎・実学混合コース)
令和6年11月7日(木)〜8日(金) 新潟県三条市:燕三条地場産業センター
・第41回施肥技術講習会(第14回基礎・実学混合コース)
令和7年2月26日(水)〜27日(木) 岡山市:岡山西川原(にしかわら)プラザ
 ◆新会員入会の件
◆新会員入会の件
2022年4月以降次の法人が入会されましたのでお知らせ致します。
<賛助会員> 入会年月
1.セントラルグリーン(株) (新潟県) 2022年4月
2.ワールドグリーン(株) (北海道) 同 上
3.九鬼肥料工業(株) (三重県) 2022年6月
4.日本製紙(株) (東京都) 同 上
5.ロイヤルインダストリーズ(株) (東京都) 同 上
6.蝶理(株) (東京都) 2022年7月
7.東洋ライス(株) (東京都) 2022年8月
8.(株)ケミカルフォース (愛知県) 同 上
9.赤城物産(株) (東京都) 2022年8月
10.関東農産(株) (栃木県) 同 上
11.(株)アイエム (東京都) 2023年4月
12.(株)クレスト (愛知県) 2023年8月
13.自然応用科学(株) (愛知県) 2024年4月
14.(株)髙村有機技研 (東京都) 2024年6月
<準会員>
1.中林肥料農薬店 (和歌山県) 2022年6月
 ◆【「地力アップ大事典」】発行のお知らせ
◆【「地力アップ大事典」】発行のお知らせ
「改訂新版 土と施肥の新知識」を出版した農文協から、「地力アップ大事典」が2022年1月に発行されます。「地力の実態」「地力とは」「地力の改善」という3本柱の構成で地力の基本から学べる有機質肥料・有機質資材便覧となっています。
添付のチラシでお申込みいただくと全肥商連会員は10%の割引になりますので、
ご購入の際にはご利用下さい。
また本書に関するお問い合わせは下記まで。
(一社)農山漁村文化協会 普及局 (担当:横山)
TEL:048-233-9339
(チラシはこちら)⇒ https://www.zenpi.jp/gyokai/pdf/jiriki_zenpi.pdf
 【新肥料法】保証票表示に係るウェブ表示について
【新肥料法】保証票表示に係るウェブ表示について
農水省では肥料法施行により、肥料の保証票等に係るウェブ表示システムの開発が終了し、これから運用の準備段階に入るということで、それに先立ち、6月14日に全肥商連本部3名とWeb(スカイプ)会議により意見交換を致しました。
内容的には、
(1) 現行表示では、指定配合肥料の使用原料表示についてすべて記載しなければならないものが、新制度では省略可能になる
(2) 生産事業場略称表示が、略称、リンク等の表示が可能になる
(3) QRコードなど、ウェブ上で保証票に記載する省略された肥料原料表示等が可能になる
(4) 保証票表示以外の商品特性や使用方法等、従来チラシなどで記載していた内容に付いても参考情報として記載が可能となる
とのことで、販売促進・差別化等に有効なツールとして活用できるのではとの印象を持ちました。会議終了後、農水省より当該表示システムの普及を目指すために、ウェブ表示を積極的に取り入れて頂ける事業者と、積極的に意見交換を行いとの意向で、本件の運用・活用についての資料を添付させて頂きます。
ご質問やご照会事項等ございましたら、全肥商連本部宛ご連絡頂ければ幸甚です。
⇒ (資料1)ウェブ表示マニュアル簡易版
https://www.zenpi.jp/gyokai/pdf/20210630_01.pdf
(資料2)見る人用マニュアル/p>
https://www.zenpi.jp/gyokai/pdf/20210630_02.pdf
 【「環境・資源・健康を考えた 土と施肥の新知識」】改訂新版のご案内
【「環境・資源・健康を考えた 土と施肥の新知識」】改訂新版のご案内
全肥商連は、施肥技術講習会で使用されている「土と施肥の新知識」の改訂新版を3月に発行致しました。
2012年に初版を出版してほぼ10年経過したことに加え、2020年に「肥料取締法」が「肥料の品質の確保等に関する法律」に改正されたことを受け、これらの状況変化に対応した内容に改めたものです。新しい肥料の分類を図表で掲載し、土壌分析結果の見方や生産現場で役立つ施肥設計の考え方などを充実させております。
今後、施肥技術講習会では、基礎コースの教本としてこの改訂新版を使用していくことになりますので、ご承知置き願います。
⇒改訂新版の概要はこちらのチラシをご参照
https://www.zenpi.jp/gyokai/pdf/20210331_01.pdf
 ●【お知らせ】「プラスチック資源循環アクション宣言」が農水省HPに掲載されました
●【お知らせ】「プラスチック資源循環アクション宣言」が農水省HPに掲載されました
近年プラスチックごみによる海洋汚染が国際的な課題となり、農林水産省では海洋プラスチック問題の解決に向け、ホームページを立ち上げ、プラスチックを使用した各業界の製造・流通、利用に関係する企業・団体などに対し、自主的取組を「アクション宣言」として表明し対応することを促しております。
肥料業界としましては、ご既承の通り被覆肥料の殻の流出防止が対象となり、既に日本肥料アンモニア協会と全国複合肥料工業会が連名で「アクション宣言」を表明し啓蒙に努めております。
3月8日(金)に本会も肥料流通団体として肥料メーカー団体の活動方針に準じた「アクション宣言」を農水省に提出し受理され、下記の通り同省ホームページに掲載されましたのでご連絡致します。
流出防止の具体的な方策に就きましては、日本肥料アンモニア協会が編集しました資料の中に、水田から濁水と被覆肥料の溶出後の殻を流出させない方法と、製造メーカーに対し包装容器に具体表示を記載し、注意喚起を促すことを明記しておりますのでご参照願います。
全肥商連としましては、農業生産者に対し製造メーカーと共にその注意喚起を更に推し進め、流出防止に努め度会員各位への周知ご協力頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
農水省のホームページはこちら
*肥料を自ら施用する者からの委託を受けて、肥料を配合する行為に係る肥料取締法上の取扱いについて*肥料の施用者委託配合に関するQ&A
肥料の配合依頼書・配合報告書の様式例はこちら
*様式例(1)配合依頼書*様式例(2)配合報告書
●【農林水産省「土づくり専門家リスト」】の公開について
農林水産省では、農業者への土づくり技術の普及を目的に、土づくりに関する資格(土壌医、施肥技術マイスター)を有する企業について「土づくり専門家リスト」を作成しHPに立ち上げました。今回は申請時間の関係上確認の取れた一部の企業のみが掲載されております。また当該地域の農業者より土づくりに関するお問合せ等がありましたら、「施肥技術マイスター」として適切なるご指導を頂きます様、お願い申し上げます。
詳しくはこちら
⇒ https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/tuti_list.html
●【普及組織と全肥商連会員会社等との連携先リスト】のデーター更新について
農水省では、昨年度から普及組織と民間企業・団体等との連携リストを農水省のホームページで公開しています。全肥商連関係では27都道府県(県部会・会社)のデーターがアップされています。
詳しくはこちら
⇒ https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/minkanlist.htm
普及組織に対するサービスの詳細等も掲載された完全版リストはこちら(PDF : 324KB)
⇒ https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/attach/pdf/minkanlist-2.pdf
●農大式土壌診断「みどりくん」の特徴と使い方(動画)掲載
農大式土壌診断「みどりくん」が新しいボトルになりました。それに伴って使い方の動画を作成、掲載しました。
●全肥商連では、2010年7月よりメールマガジンを発行して会員への情報サービスを実施しています。配信希望の方は会員コーナーのTOPページからご登録ください(会員コーナーへは全肥商連会員の方しかはいれません)。
更新情報
- 2024/07/11
- 有機肥料懇話会691回(2024年6月)を更新しました。
- 2024/07/04
- TOPページ(TOPICS)、行事予定を更新しました。
- 組織案内を更新しました。
- 2024/06/04
- TOPページ(TOPICS)、行事予定を更新しました。
- 第39回全肥商連施肥技術講習会(第12回基礎・実学混合コース)を更新しました。
- 2024/05/10
- TOPページ(TOPICS)、行事予定を更新しました。
- 2024/05/07
- 組織案内を更新しました。
- 2024/04/24
- TOPページ(TOPICS)を更新しました。
- 2024/04/19
- 行事予定を更新しました。
- 2024/04/09
- 有機肥料懇話会690回(2024年3月)を更新しました。
- 2024/04/03
- TOPページ(TOPICS)、行事予定を更新しました。
- 施肥技術講習会のお知らせを更新しました。
- 2024/03/08
- TOPページ(TOPICS)、行事予定を更新しました。
- 2024/02/27
- 第38回全肥商連施肥技術講習会(第11回基礎・実学混合コース)を更新しました。
- 2024/02/09
- TOPページ(TOPICS)、行事予定を更新しました。
- 2024/01/15
- TOPページ(TOPICS)、行事予定を更新しました。
- 有機肥料懇話会689回(2023年12月)を更新しました。
- 2024/01/01
- 会長挨拶を更新しました。
- 2023/12/27
- 令和5年全肥商連十大ニュースを更新しました。















 (1)都道府県部会
(1)都道府県部会-
- ◇今後の都道府県部会総会開催予定
- 令和6年7月25日(木)
滋賀県部会総会
@ホテルニューオウミ
山森会長、西出専務- 令和6年8月6日(火)
栃木県部会総会
@ベルヴィ宇都宮
山森会長、西出専務- 令和6年8月29日(木)
山形県部会総会
@ホテルサンチェリー
山森会長、西出専務 - ◇今後の都道府県部会総会開催予定
 (2)本部
(2)本部-
- ◇今後の予定
- 令和6年8月26日(月)
理事会
@めっきセンター
山森会長他2名- 令和6年9月10日(火)
定時社員総会・理事会
@東京ガーデンパレス- 令和6年11月7日(木)〜8日(金)
第40回施肥技術講習会(第13回基礎・実学混合コース)
@燕三条地場産業センター(新潟県三条市) - ◇今後の予定